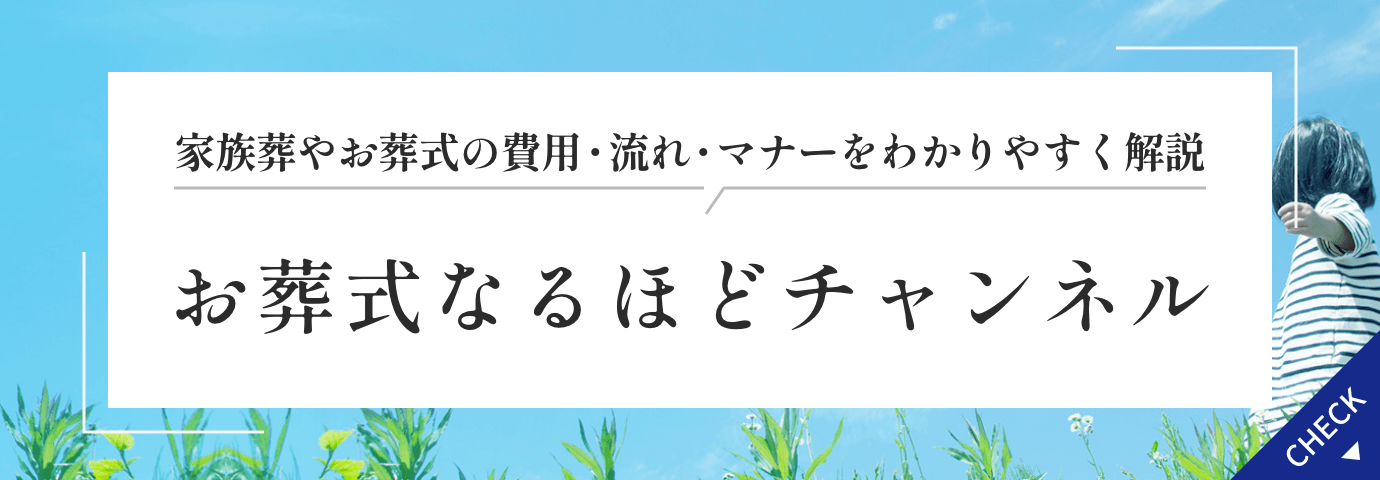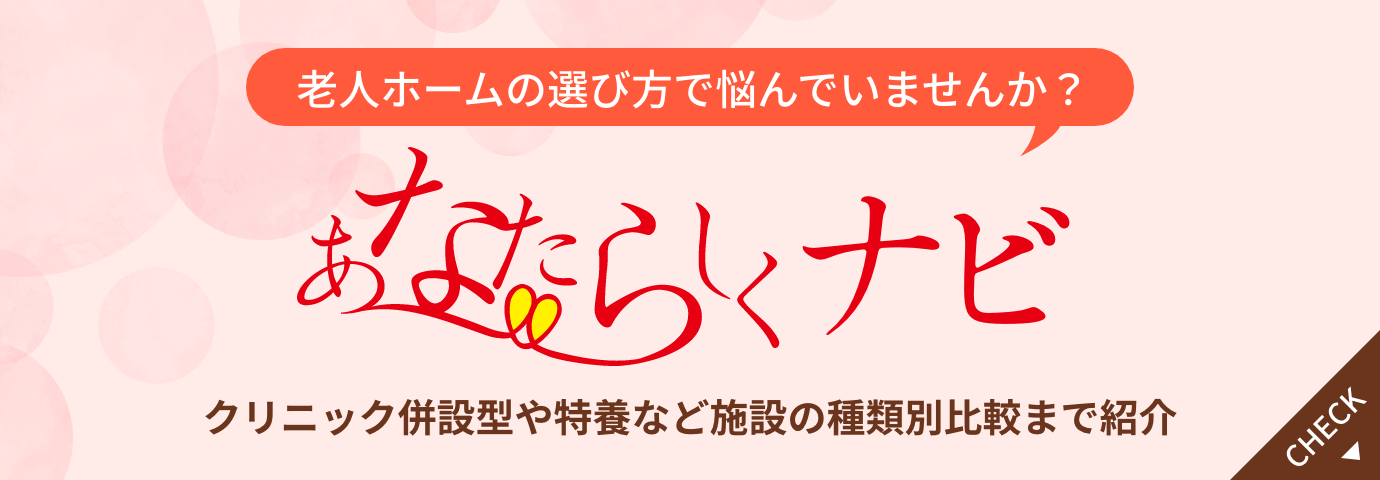葬儀は人生で何度も経験するものではないため、費用の相場や内容について事前に把握している方は多くありません。
いざ準備が必要になった際に、どのくらいの費用がかかるのか、形式によってどのような違いがあるのかを知らないまま進めてしまうと、予算面や内容面で不安を抱えることもあります。
葬儀の費用は式の形式や規模、参列者の人数などによって大きく変わるため、「一般葬・家族葬・直葬」の特徴を理解しておくことが大切です。
本記事では、全国的な葬儀費用の「相場」や「形式ごとの特徴」、さらに「費用を抑えるための工夫」について詳しく解説していきます。
葬儀費用の全国平均とは?
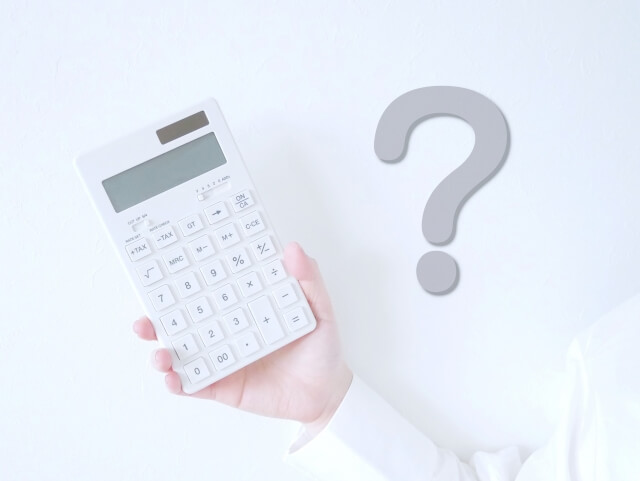
葬儀費用の全国平均は、鎌倉新書が発表した「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」によると118万5,000円となっています。(参考:第6回お葬式に関する全国調査)
内訳は式場や祭壇などの基本料金が大部分を占め、加えて飲食費や返礼品といった付随費用が含まれます。
なお、2022年の同調査では110万7,000円まで下がっていましたが、コロナ禍が落ち着いて参列者が増えたことで再び上昇しました。
こうした推移からも分かるように、全国平均は一定ではなく、社会情勢や葬儀の形式の違いによって変動します。
平均値を正しく把握しておくことは、急な準備の際に落ち着いて判断するための大切な目安となるでしょう。
葬儀形式別の費用相場

葬儀の費用は、選ぶ形式によって大きく変動します。
参列者の人数や儀式の規模、用意する会場や返礼品の内容によって総額が異なるため、一般葬・家族葬・直葬それぞれの特徴と費用の目安を把握しておくことが重要です。
参考:【葬儀の費用はいくらかかるの?】知っておきたいポイントを解説 | 終活スタイル
一般葬
一般葬は、通夜と告別式を二日間にわたり行い、多くの参列者を迎える最も伝統的なスタイルです。
親族だけでなく、友人や会社関係者、地域の知人など幅広い人々が参列するため、式場の広さや祭壇の規模、会葬返礼品や飲食費用などが大きく影響します。
結果として、総額は100万〜200万円程度になることが一般的で、費用面では最も高くなる傾向があります。
第6回お葬式に関する全国調査(2024年)でも、一般葬は他形式より平均費用が高いと示されており、社会的なつながりを大切にする家庭で選ばれることが多い形式です。
ただし、近年は負担軽減のために一般葬を縮小する動きもあり、事前にプランを比較検討することが求められます。
家族葬
家族葬は、親族やごく親しい友人のみで行う小規模な葬儀です。
一般葬と比べると参列者が少ないため、返礼品や飲食費が抑えられ、費用は50万〜150万円ほどに収まるケースが多く見られます。
特に60万〜80万円程度で行われることが一般的とされ、全国調査でも平均は約105万7千円と報告されています(参考:第6回お葬式に関する全国調査)。
また、家族葬は「ゆっくり故人と向き合える」「準備や対応の負担が少ない」といった理由で選ばれることが多く、コロナ禍以降は一般葬に代わって主流の形式となりつつあります。
ただし、参列できなかった方が後日弔問に訪れるケースも多く、事前に親族や関係者と意思を共有しておくことが大切です。
直葬(火葬のみ)
直葬は、通夜や告別式を行わず、火葬のみで故人を見送るシンプルな形式です。
宗教儀式や会場設営が不要なため費用は大幅に抑えられ、10万〜50万円程度で済むケースが多く、特に20万〜40万円の範囲に収まる事例が目立ちます。
近年は経済的な事情や「簡素で良い」という価値観の広がりから選ばれる機会が増えてきました。
また、都市部では直葬専用のプランを用意する葬儀社も増えており、利便性の高さも後押ししています。
ただし、儀式を行わないため、宗教的な儀礼を重視する家庭には合わない場合もあり、事前に親族間でしっかり話し合うことが求められます。
葬儀費用の内訳

葬儀の費用は、大きく「式場使用料」「祭壇・供花」「火葬料」「会葬返礼品・飲食費」の4つに分けられます。
それぞれの費用について解説します。
式場使用料
式場使用料は、斎場やホールを利用するための費用であり、葬儀費用の中心を占めます。
この項目には棺、祭壇、遺影、搬送車、ドライアイスなど基本的なサービスが含まれており、葬儀一式費用としてまとめて請求されることが多いのが特徴です。
鎌倉新書の調査によれば、葬儀一式費用の全国平均は75万7,000円で、総額の半分以上を占めることが示されています(参考:葬儀費用の平均相場はいくら?料金の内訳や葬式代を安くするコツを紹介)。
公営斎場は数万円程度と比較的安価であるのに対し、民営の葬儀ホールを利用すると設備やサービスの充実度に比例して高額になる傾向があります。
費用を抑えるためには、希望する規模に応じて複数の会場を比較検討することが有効です。
祭壇・供花
祭壇と供花は、葬儀の印象を大きく左右する装飾費用です。
白木祭壇を利用すれば費用を抑えられる一方で、生花祭壇や大型の装花を希望すると追加費用が数十万円単位でかかる場合もあります。
また、親族や知人から供花の注文が多いと会場全体に花が増え、費用も膨らみやすくなります。
日比谷花壇の解説によると、祭壇や供花の費用は数万円から数十万円規模まで幅広いことが確認されています。(参考:お葬式にはいくらかかる?葬儀費用の平均相場や内訳を解説)
見積もりを見る際には「祭壇代」「供花代」が基本プランに含まれているのかを確認することが重要です。
過剰な装飾を避け、自分たちの希望に沿った形を選ぶことで、費用を必要以上に増やさずに済みます。
火葬料
火葬料は、地域や施設によって大きく異なる費用です。
公営火葬場を利用する場合は数千円〜数万円程度で済むことが多い一方、都市部の民営火葬場では数万円から10万円程度かかることもあります。
鎌倉新書の調査でも、火葬料は葬儀一式費用に含まれる場合と、別途計上される場合があることが報告されています(参考:葬儀費用の平均相場はいくら?料金の内訳や葬式代を安くするコツを紹介)。
事前に自治体や葬儀社へ確認し、費用が含まれているかどうかを把握することが、予算管理に欠かせません。
会葬返礼品・飲食費
参列者への返礼や飲食は、人数に比例して大きく膨らむ費用項目です。
香典返しは一人ひとりに渡す必要があるため、参列者が多い一般葬では特に高額になります。
鎌倉新書の調査では、返礼品の平均は22万円、飲食費は20万7,000円と報告されており、葬儀費用全体における大きな割合を占めています。
通夜ぶるまいや精進落としといった食事も、人数が増えるほど負担が大きくなるため、規模を抑えたい場合には会食を簡素にするなど調整が必要です。
逆に、家族葬や直葬では人数が限られるため、この費用は軽減されます。
参列者の範囲を事前に決めておくことが、費用を無理なく抑えるポイントになります。
葬儀費用を抑える方法

葬儀にかかる費用は全国平均で100万円を超えるとされているため、家庭にとっては大きな負担になり得ます。
しかし、事前に準備をしておくことで想定外の出費を避けたり、複数のプランを比較して無駄を省いたりすることで、必要以上に費用をかけずに済む方法があります。
さらに、互助会などの仕組みを活用することで割引や特典を受けられる場合もあるでしょう。
ここでは、具体的に費用を抑えるための「3つ」の方法を見ていきましょう。
生前に準備しておく
葬儀は突然必要になることが多いため、慌てて手配をすると割高なプランを選んでしまうケースがあります。
その点、生前から準備を進めておけば、冷静に比較検討でき、結果として無駄を減らせます。
例えば、葬儀社が提供する会員制度に加入すると、基本料金が割引になるケースがあり、入会金数千円から数万円で将来的に10〜20万円ほど安くなることもあります。(参考:葬儀代金にも割引がある!お得にできる方法や割引の仕組みについて紹介)
また、葬儀保険や積立型の商品を利用すれば、遺族に急な負担をかけずに済むのもメリットです。
生前の準備は「経済的な安心」と「精神的な安心」の両方をもたらしてくれる手段といえるでしょう。
プランを比較する
葬儀社によって提示されるプランは内容も価格も異なります。
同じ「家族葬」でも、含まれる祭壇や返礼品の内容によって総額に数十万円の差が出ることも少なくありません。
そのため、必ず複数の葬儀社やプランを比較し、不要なオプションが含まれていないか確認することが大切です。
特に互助会のプランは月々の掛け金で利用できる点が魅力的ですが、基本価格が高めに設定されている場合もあり、結果的に割高になることがあります。
また、葬儀後に追加請求が発生するケースもあるため、契約前に見積書を丁寧にチェックすることが欠かせません。
比較を怠らなければ、数十万円単位の節約につながる可能性があります。
互助会を活用する
互助会は、毎月少額を積み立てることで葬儀や結婚式などに利用できる制度です。
提携している会場や葬儀社を割安で利用できるほか、会員特典として祭壇や式場費用が優遇される場合があります。
さらに、積み立てた資金は冠婚葬祭全般に使えることが多いため、使い勝手の良さも魅力です。
ただし、解約時には払い戻し額が掛け金より少なくなることが多く、また希望する葬儀スタイルが必ずしも選べない場合もあります。
そのため、契約前に内容をよく確認し、家族にも説明しておくことが重要です。
上手に利用すれば費用の大幅な軽減につながりますが、仕組みを理解せずに加入すると不満につながる恐れもあるため注意が必要です。
まとめ
葬儀に関する不安は、準備不足や情報不足が原因であることが少なくありません。
しかし、信頼できる情報や選択肢を手に入れることで、その不安はずっと小さくなります。
例えば、「互助会」への事前加入を検討することで、葬儀費用を一般価格より30~50%割引で備える選択肢もあります(参考:互助会のごじょスケ)。
少額の掛け金を積み立て、いざという時に安心できる備えができるのは、精神的にも大きな支えになります。
そこでおすすめなのが、全国の互助会をまとめて比較できるポータルサイト「ごじょスケ」です。
住所を入力するだけで対応可能な互助会の資料を請求でき、葬儀費用やサービス内容を効率よく比較できます。
エンディングノートのプレゼントもあるため、初めての方にもおすすめです。
参考:【エンディングノートとは?】エンディングノートにはいつ何を書けばいいのか | 終活スタイル
まずは気になる資料を取り寄せて、複数の互助会プランを比較検討し、納得のいく備えをスタートさせてみてください。